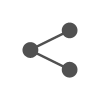フォックスコン、自動車生産に参入
三菱ブランドで発売へ
その名は「モデルB」

業界で長らく注目されてきたアップルカー構想は頓挫したものの、その流れを汲むかのような新たな車両が登場し、再び話題を集めている。その正体は、iPhoneの製造元として知られる台湾・フォックスコンが開発した電気自動車だ。フォックスコンが三菱ブランドの電気自動車をオーストラリア市場に供給する見通しとなり、自動車業界に衝撃を与えている。電子機器のOEMメーカーから電動車両メーカーへの転身を図るフォックスコンは2026年上半期に自社開発のハッチバックEVを日本の自動車ブランドとして発表する予定だ。
国内メディアは、この車両が三菱ブランドで発売されると報じており、三菱にとっては一時途絶えていたEVラインナップを再構築する契機になると期待されている。この提携に関する報道は、自動車専門メディアによって明らかになった。フォックスコン幹部で日産出身の関潤氏は、同社のEV生産計画に関する説明の中で、「日本ブランド向けのモデルBの生産が決定し、この車両はオーストラリア市場で展開される」と語っている。三菱側は「確定事項はない」との立場をとっているものの、業界では両社の本格的な提携は時間の問題と見る声が多い。

キアEV3と直接競合
空白の多いラインナップを補完
フォックスコンのモデルBは、全長4,300mm台・ホイールベース2,800mm台というサイズの小型EVハッチバック。キアEV3やMG ZS EVと直接競合するポジションとなる。デザインは世界的カロッツェリアのピニンファリーナが手がけ、60kWhのバッテリーを搭載。NEDC基準で500km以上の航続距離を実現する。実用性と効率性を兼ね備えたこのモデルは、オーストラリア市場で普及型EVとしての役割を担うと見られている。
このモデルBは三菱の現行ラインナップにおける空白を埋める存在としても注目される。かつてi-MiEVでEV市場に先駆けて参入した三菱だが、近年はPHEVに注力してきた。アウトランダーPHEVやエクリプスクロスPHEVが一定の人気を得ていたものの、エクリプスクロスの生産終了、ASXやパジェロスポーツの撤退などにより、EVおよび小型SUVのラインは事実上空白になっている。さらに、オーストラリア政府は7月1日から新たな燃費基準を導入し、CO₂排出に対する規制を強化。これにより三菱にとっての負担は一層増すことになりそうだ。

電子機器の限界を突破する狙い
世界にEVを供給する戦略か
今回の提携の中心にいるフォックスコンはもはや単なる電子機器メーカーではない。数年前からEV製造技術の確立に向け、積極的な投資と開発を進めており、自社ブランド「Foxtron」のもと、モデルA・B・Cといったラインナップを展開している。中でもモデルBはOEM供給やリブランディングに最適化されたプラットフォームとして、他社ブランド向けに提供される可能性が最も高い。
フォックスコンは過去に日産との資本提携交渉も行っていたが、最終的にはパートナーシップを重視する方向にシフト。ルノーやホンダとの協議も検討していることを明らかにしていた。今回の三菱との協業が進展すれば、フォックスコンのEV戦略が実際に形となり始めることになる。なお、現時点では中型SUVのモデルCや小型のモデルAなど、その他のモデルについて三菱ブランドでの展開は未定。とはいえ、この提携がフォックスコンにとって世界市場におけるOEMプレイヤーとしての地位を確立する転換点となる可能性は高い。

三菱を牽引する主役となるか
品質管理体制の確立が鍵
2026年にモデルBが実際に発売されれば、三菱にとっては単なる新型EVの導入を超え、ブランド再構築の起点となる可能性がある。オーストラリア市場では現在、PHEVからEVへの移行が急速に進行しており、中国系の低価格EVがシェアを拡大。伝統ブランドは厳しい競争にさらされている。こうした状況でフォックスコンとの提携は、三菱にとって柔軟性と競争力を獲得する大きなチャンスとなるかもしれない。
ただし、OEMベースの車両開発ではブランドとしての一貫性や品質基準の維持が極めて重要。フォックスコンの品質管理体制が自動車業界でも機能するか、そして三菱がその技術を自社の哲学にどう落とし込むかが成否を左右することになる。確かなのは、自動車産業の重心が着実に変化し始めているということ。そして、その変化の渦中に、フォックスコンと三菱の名が新たに浮かび上がってきている。