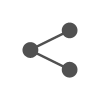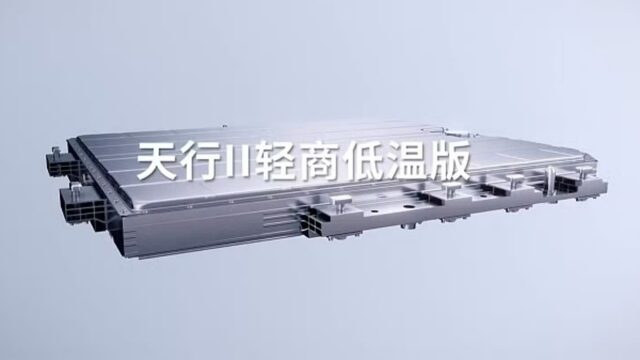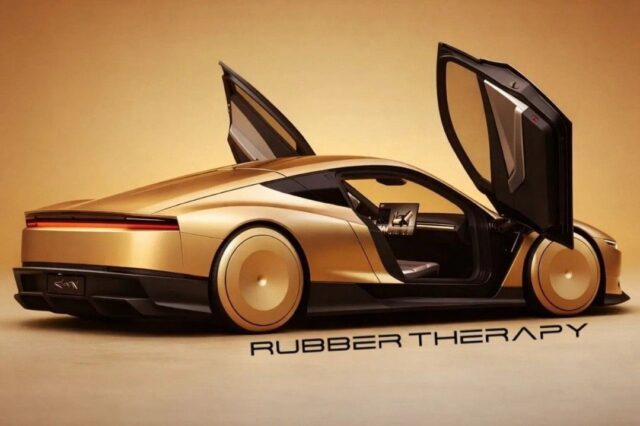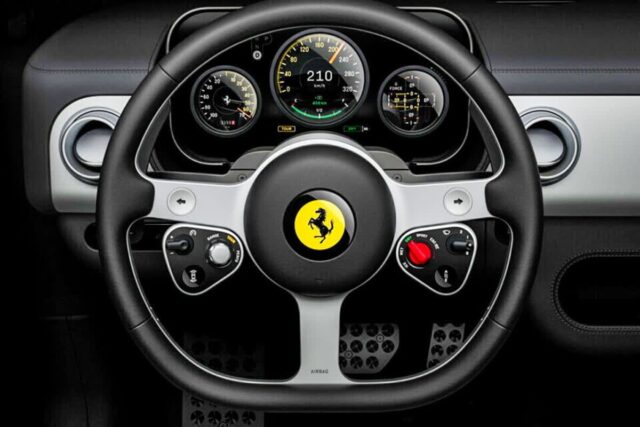【引用:Depositphotos】出退勤時の道路で、事故も工事もないのに急に流れが詰まり、わずか数メートルずつしか進まない状況に遭遇した経験は多いだろう。日本の運転手も前走車が止まっているから渋滞が起きると考えがちだが、実際には先頭車両はほぼ減速すらしていない場合が多い。渋滞とは前方の明確な原因よりも、後方から伝播する速度変動の波によって形成される、典型的な誤解されやすい現象である。

【引用:Depositphotos】専門家によると、渋滞は単なる車線数や合流部だけの問題ではなく、道路設計、信号制御、交差点構造、周囲の地形など、多数の要素が複合的に絡むと指摘している。高速道路1車線あたりの通過可能台数は約2,250〜2,400台、信号のある幹線道路では790〜1,110台にまで落ち込み、交通需要との不一致がボトルネックを生む。日本でも同様の条件は多く、構造的限界が渋滞を誘発する点は共通している。

【引用:Depositphotos】さらに、先頭車両は正常に流れていても、後続車がわずかな速度変化に過敏に反応すると、減速の尾が連鎖して渋滞が形成される。いわゆるゴースト渋滞である。海外の実験では、円形コースで一定間隔を保ち走行したにもかかわらず、誰一人ブレーキを強く踏んでいないのに渋滞波が自然発生した。これは日本の高速道路でも日常的に見られ、急加速・急減速、不要な車線変更が交通流を切断する典型例となる。

【引用:Depositphotos】こうした渋滞を解消するには道路システムだけでは不十分であり、世界各国がITS導入や信号最適化など技術的対策を進めている一方、根本的な鍵は結局「運転者の行動」にあると専門家は指摘する。車間維持、滑らかな速度調整、合流部での無理な割り込み回避といった基本動作が、渋滞を作るか抑えるかを左右する。目の前の車より、自分が交通流全体にどう影響を与えているのかを意識することこそ、渋滞を減らす第一歩だ。