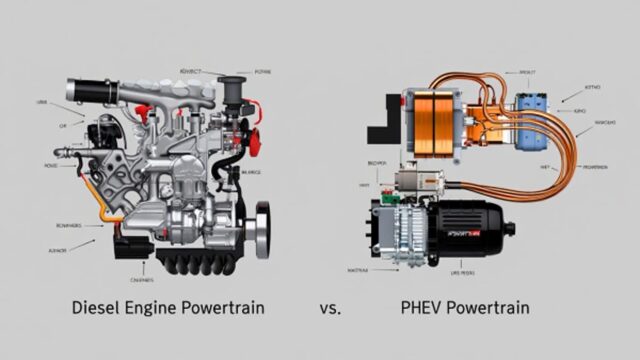【引用:depositphotos】現代の車両は整備周期ごとに警告灯で工場訪問を促すが、多くは運転席でリセット可能だ。整備必要警告灯は約2万4,000kmで点灯し、実質的にはエンジンオイル交換時期の通知に過ぎない。自分で交換後に点滅が続く場合は取扱説明書でリセットでき、OBD2スキャナーを使えば給油口キャップの緩みや内部ECUの実際のトラブルも判別できる。

【引用:depositphotos】ブレーキ整備では、パッド交換時にキャリパー圧縮と同時にブリーダーバルブを開くことで古いブレーキ液の逆流を防ぎ、ABSモジュール損傷を回避できる。汚れたブレーキ液は制動応答を悪化させ、放置すると高額修理につながる。

【引用:depositphotos】燃料・エンジンオイル添加剤は、ガソリン車では既存添加剤で十分なことが多く不要なケースが多い。ディーゼル車では寒冷時の燃料凝固防止やインジェクター清掃に一定効果があるが、仕様を確認せず乱用するとコスト浪費となる。燃料品質が悪い地域のみ、テクロンやシーフォームなどが有効な場合がある。

【引用:depositphotos】暖房から冷風しか出ない場合はヒーターコア故障ではなくクーラント液不足が一般的原因である。リザーブタンクの確認が最優先で、空気混入によりヒーターコアへ温かいクーラントが循環しなくなるためだ。バッテリーは保管中も劣化するため、製造1か月以内のものを選び、取り付け前に短時間充電し端子を清潔に保つ必要がある。

【引用:depositphotos】点火プラグは最大16万km使用可能だが、摩耗や炭素堆積で加速力低下・アイドリング不安定・燃費悪化が起こる。燃料タンクは満タン自動停止後の追い給油をすると蒸発ガス回収装置を損傷する危険があり、停止したら即給油を終えるべきだ。

【引用:depositphotos】エアフィルターは詰まると空気供給不足で性能と燃費に影響し、2万〜2万4,000kmでの点検・交換が推奨される。PCVバルブは内部圧力とスラッジ発生を防ぐ重要部品で、1万6,000〜2万4,000kmごとに点検し、振って音がしない・空気が通らない場合は交換する。

【引用:depositphotos】エンジンオイルはマニュアルの基準に従い、合成油では約1万9,000kmが目安。ミッションオイルは8万〜14万5,000kmで交換が推奨される。タイヤ空気圧は毎月1psi程度自然低下するため月1回点検が必要で、位置交換は1万3,000〜1万9,000kmごとが望ましい。ブレーキ液は吸湿性が高く2〜3年ごとに交換が必要で、ベルト・ホースは月次点検で亀裂・膨張・漏れを確認することが重大故障の予防になる。